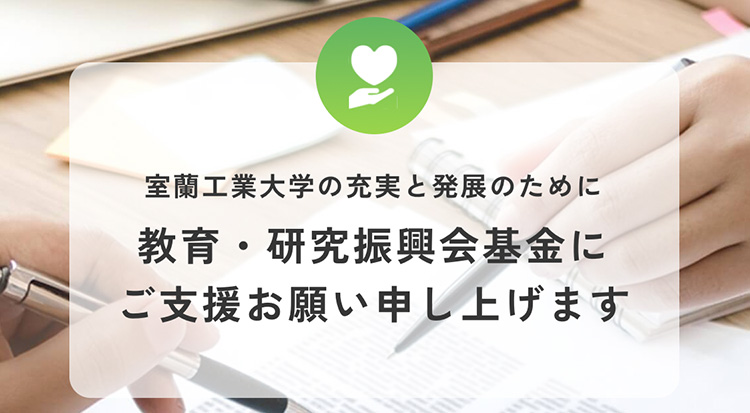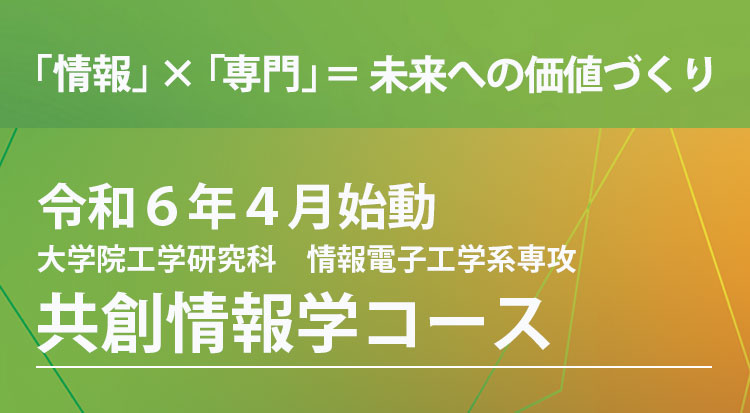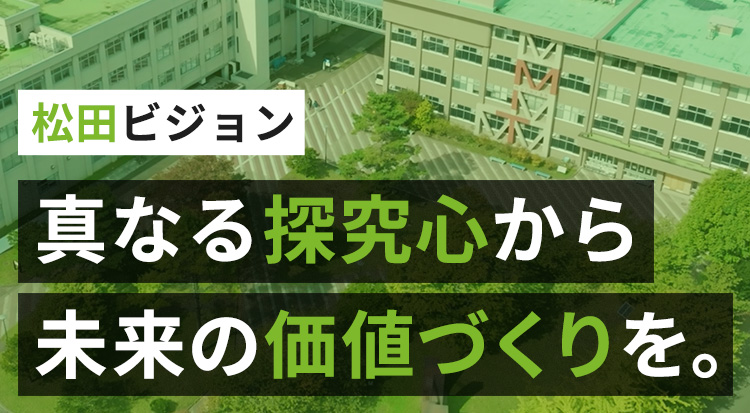MURORAN
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
真なる探究心から未来の価値づくりを。
重要なお知らせ
NEWS 室工大ニュース
INFORMATION
- 2024.04.25 入試情報 2024年度10月入学・2025年度4月入学大学院博士前期課程外国人留学生入試(国外出願)学生募集要項の公表について
- 2024.04.19 お知らせ AI・DX人材育成に関するシンポジウムを開催します
- 2024.04.18 お知らせ 室蘭工業大学創立75周年記念・蘭岳コンサート15周年記念「第49回蘭岳コンサート」を開催します【令和6年7月13日(土)】
- 2024.04.18 プレスリリース 令和7年度入学者選抜 総合型選抜(昼間コース)における女子枠の創設について
- 2024.04.18 お知らせ 令和7年度入学者選抜 総合型選抜(昼間コース)における女子枠の創設について(予告)
- 2024.04.18 お知らせ 道新室蘭政経文化懇話会において内海航空宇宙機システム研究センター長が日本の宇宙開発の現状等に関する講演を行いました
- 2024.04.18 お知らせ 院価値再発見Campaign2024がスタートしました
- 2024.04.16 お知らせ 浅田研究室が開発した技術が国土交通省「点検支援技術性能カタログ」に掲載されました
- 2024.04.15 入試情報 令和7年度理工学部編入学学生募集要項の公表について
- 2024.04.12 お知らせ 本学サークルによる学生実験について
- 2024.04.19 お知らせ AI・DX人材育成に関するシンポジウムを開催します
- 2024.04.18 お知らせ 室蘭工業大学創立75周年記念・蘭岳コンサート15周年記念「第49回蘭岳コンサート」を開催します【令和6年7月13日(土)】
- 2024.04.18 お知らせ 令和7年度入学者選抜 総合型選抜(昼間コース)における女子枠の創設について(予告)
- 2024.04.18 お知らせ 道新室蘭政経文化懇話会において内海航空宇宙機システム研究センター長が日本の宇宙開発の現状等に関する講演を行いました
- 2024.04.18 お知らせ 院価値再発見Campaign2024がスタートしました
- 2024.04.16 お知らせ 浅田研究室が開発した技術が国土交通省「点検支援技術性能カタログ」に掲載されました
- 2024.04.12 お知らせ 本学サークルによる学生実験について
- 2024.04.11 お知らせ 東京事務所 臨時閉所のお知らせ【令和6年5月10日(金)】
- 2024.04.11 お知らせ 令和6年度入学宣誓式を挙行しました
- 2024.04.05 お知らせ 室蘭工業大学、学生の多様な学び、教職員の多様な働き方を実現するためのコンテンツ管理基盤としてBoxを全学導入
- 2024.04.25 入試情報 2024年度10月入学・2025年度4月入学大学院博士前期課程外国人留学生入試(国外出願)学生募集要項の公表について
- 2024.04.18 入試情報 令和7年度入学者選抜 総合型選抜(昼間コース)における女子枠の創設について(予告)
- 2024.04.15 入試情報 令和7年度理工学部編入学学生募集要項の公表について
- 2024.01.19 入試情報 2024年度10月入学 コンピュータ科学×専門分野でスマート社会を牽引するイノベーション人材育成プログラム入試(CS×専門プログラム入試)学生募集要項の公表について
- 2024.01.11 入試情報 令和6年能登半島地震に関する室蘭工業大学の対応について(まとめ)
- 2023.11.28 入試情報 空閑良壽×梶田隆章 特別対談「新時代に求められる人材」とは?
- 2023.10.17 入試情報 2025年度大学院博士後期課程入学試験一般入試及び社会人入試における外国語科目の変更について(予告)
- 2023.10.06 入試情報 「令和 7 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト及び個別学力検査等 の配点について(予告)」資料の訂正について
- 2023.09.26 入試情報 2024年度10月入学大学院博士後期課程CSC-MuroranIT奨学金入試学生募集要項の公表について
- 2023.09.26 入試情報 2024年度10月入学大学院博士後期課程外国人留学生入試(国外出願)学生募集要項の公表について
- 2024.04.18 プレスリリース 令和7年度入学者選抜 総合型選抜(昼間コース)における女子枠の創設について
- 2024.04.05 プレスリリース 室蘭工業大学、学生の多様な学び、教職員の多様な働き方を実現するためのコンテンツ管理基盤としてBoxを全学導入
- 2024.02.27 プレスリリース 太田香教授が令和5年度北海道科学技術奨励賞を受賞しました
- 2024.02.08 プレスリリース アシル-トイタによる心と体に響く新しい食の価値共創拠点 第2回ワークショップ&第3回CCCワークショップを開催します
- 2024.01.31 プレスリリース SPACE INDUSTRY SEMINAR IN MURORAN~ものづくりのまち室蘭が挑戦する~を開催します
- 2023.12.22 プレスリリース 東京⼯業⼤学・室蘭⼯業⼤学・九州⼯業⼤学が科学技術に関する産学・⼈材育成連携覚書を締結しました −⽇本を横断する三⼤学、地域の特性を活かし連携−
- 2023.11.30 プレスリリース 本学卒業生が日本銅学会第57回論文賞を受賞しました
- 2023.11.24 プレスリリース 令和5年度第2回定例記者懇談会を実施します
- 2023.11.22 プレスリリース コラボ企画!TENTOで「ムロぴょんホットサンド第1弾」を販売します
- 2023.11.19 プレスリリース 太田香教授が第5回輝く女性研究者賞(科学技術振興機構理事長賞)を受賞しました
- 2024.04.04 研究 趙 越准教授が第8回応用物理学会フォトニクス奨励賞を受賞しました
- 2024.03.22 研究 名古屋大学 液液デトネーションエンジン 宇宙実証用フライトモデルの最終燃焼試験を白老実験場で実施しました
- 2024.03.18 研究 内閣府事業「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」第3期『スマートモビリティプラットフォームの構築』に採択されました
- 2024.02.26 研究 「第4回地域の公共交通リ・デザイン実現会議」(国土交通省)で有村教授が講演しました
- 2024.01.23 研究 科学技術振興機構(JST)の先端国際共同研究推進事業「次世代のための ASPIRE」通信分野に太田香教授の「6Gのための超次元的情報通信技術の創出 」が採択されました
- 2023.12.18 研究 名古屋大学との共同研究「液液デトネーションエンジンの燃焼試験」を実施しました
- 2023.11.01 研究 横須賀高校の生徒が白老実験場を訪問しました
- 2023.10.24 研究 国立工業大学長が白老エンジン実験場を視察しました
- 2023.10.11 研究 航空宇宙機システム研究センター 内海政春 教授が日本学術会議「未来の学術振興構想(2023年度版)」の「学術の中長期研究戦略」に採択されました
- 2023.09.12 研究 JAXA/ISASと探査機の天体着陸・再浮上試験を実施しました
- 2024.04.18 連携 道新室蘭政経文化懇話会において内海航空宇宙機システム研究センター長が日本の宇宙開発の現状等に関する講演を行いました
- 2024.03.22 連携 名古屋大学 液液デトネーションエンジン 宇宙実証用フライトモデルの最終燃焼試験を白老実験場で実施しました
- 2024.03.18 連携 日本政策金融公庫と連携協力に関する協定及び大規模災害時等における業務連携に関する覚書を締結しました
- 2024.02.13 連携 MONOづくりみらい共創機構 機構創立記念シンポジウムを開催します
- 2024.01.29 連携 「北海道若者活躍プロジェクト」の事業成果報告書について
- 2023.12.22 連携 室蘭工業大学、東京工業大学および九州工業大学による科学技術に関する産学・人材育成連携覚書締結式・三工大連携シンポジウムを開催しました
- 2023.12.22 連携 東京⼯業⼤学・室蘭⼯業⼤学・九州⼯業⼤学が科学技術に関する産学・⼈材育成連携覚書を締結しました −⽇本を横断する三⼤学、地域の特性を活かし連携−
- 2023.12.18 連携 名古屋大学との共同研究「液液デトネーションエンジンの燃焼試験」を実施しました
- 2023.11.02 連携 「北海道立札幌医科大学・国立大学法人室蘭工業大学 デジタル医工連携セミナー」を開催しました
- 2023.10.30 連携 国立アイヌ民族博物館と包括連携協定を締結しました
EVENT
- 2024.04.19 イベント案内 AI・DX人材育成に関するシンポジウムを開催します
- 2024.04.18 イベント案内 室蘭工業大学創立75周年記念・蘭岳コンサート15周年記念「第49回蘭岳コンサート」を開催します【令和6年7月13日(土)】
- 2024.03.22 イベント報告 ロボットアリーナ2月体験教室「LEGO®ブロックでサッカーをしよう!」を開催しました
- 2024.03.18 イベント報告 日本政策金融公庫と連携協力に関する協定及び大規模災害時等における業務連携に関する覚書を締結しました
- 2024.03.08 イベント報告 2023年度留学生交流推進懇談会及び留学生交流会を開催しました
- 2024.03.07 イベント報告 アシル-トイタによる心と体に響く新しい食の価値共創拠点 第2回ワークショップを開催しました
- 2024.03.07 イベント報告 「理系国立大学について知ろう!室蘭工業大学説明会~室蘭工業大学の研究と学びについて~」説明会が山脇学園中学高等学校で開催されました
- 2024.03.06 イベント報告 STARTUP 2024 in 室蘭工業大学「室蘭から世界へ!」 学内ベンチャー育成塾 プレイベント を開催しました
- 2024.03.04 イベント報告 MONOづくりみらい共創機構創立記念シンポジウムを開催しました
- 2024.03.04 イベント案内 「日本海水学会若手会第15回学生研究発表会」が開催されます
- 2024.04.19 イベント案内 AI・DX人材育成に関するシンポジウムを開催します
- 2024.04.18 イベント案内 室蘭工業大学創立75周年記念・蘭岳コンサート15周年記念「第49回蘭岳コンサート」を開催します【令和6年7月13日(土)】
- 2024.03.04 イベント案内 「日本海水学会若手会第15回学生研究発表会」が開催されます
- 2024.02.22 イベント案内 「Startup Weekend 伊達」(室蘭工業大学SIP)を開催します
- 2024.02.13 イベント案内 MONOづくりみらい共創機構 機構創立記念シンポジウムを開催します
- 2024.02.09 イベント案内 令和5年度合同業界研究会を開催します【令和6年2月13日(火)・14日(水)】
- 2024.02.08 イベント案内 アシル-トイタによる心と体に響く新しい食の価値共創拠点 第2回ワークショップ&第3回CCCワークショップを開催します
- 2024.02.02 イベント案内 STARTUP 2024 in 室蘭工業大学「室蘭から世界へ!」 学内ベンチャー育成塾 プレイベント を開催します
- 2024.01.31 イベント案内 SPACE INDUSTRY SEMINAR IN MURORAN~ものづくりのまち室蘭が挑戦する~を開催します
- 2023.12.27 イベント案内 第29回室蘭工業大学学長杯争奪ロボットサッカーコンテストを開催します
- 2024.03.22 イベント報告 ロボットアリーナ2月体験教室「LEGO®ブロックでサッカーをしよう!」を開催しました
- 2024.03.18 イベント報告 日本政策金融公庫と連携協力に関する協定及び大規模災害時等における業務連携に関する覚書を締結しました
- 2024.03.08 イベント報告 2023年度留学生交流推進懇談会及び留学生交流会を開催しました
- 2024.03.07 イベント報告 アシル-トイタによる心と体に響く新しい食の価値共創拠点 第2回ワークショップを開催しました
- 2024.03.07 イベント報告 「理系国立大学について知ろう!室蘭工業大学説明会~室蘭工業大学の研究と学びについて~」説明会が山脇学園中学高等学校で開催されました
- 2024.03.06 イベント報告 STARTUP 2024 in 室蘭工業大学「室蘭から世界へ!」 学内ベンチャー育成塾 プレイベント を開催しました
- 2024.03.04 イベント報告 MONOづくりみらい共創機構創立記念シンポジウムを開催しました
- 2024.02.26 イベント報告 「第4回地域の公共交通リ・デザイン実現会議」(国土交通省)で有村教授が講演しました
- 2024.02.26 イベント報告 第5回コラボ産学官会員大学による情報交換会で広報室が講演しました
- 2024.01.25 イベント報告 大学改革セミナー「室工大未来塾」を開催しました