室工大ニュース
『ウイルタ語音声資料』(Muroran Working Papers in Liguistics, No.2)を発行しました
令和7年3月28日(金)、室蘭工業大学ひと文化系領域から、データCD付の報告書『ウイルタ語音声資料』(山田祥子(採録・訳注)/Muroran Working Papers in Liguistics, No.2)を発行しました。これはJSPS科研費研究活動スタート支援「ウイルタ語の統合的な記録・記述と資料化:音声・グロス・訳付き資料の作成と公開」(代表:山田祥子、課題番号23K18668)(2023-2024年度)の成果の一部です。
研究の概要
ウイルタ語は、サハリン(樺太)島の先住民族ウイルタ(旧称オロッコ)の固有の言語です。方言は北方言と南方言に分類されます。
ウイルタは、トナカイ飼育を伝統的な生業とし季節移動をしながら暮らしていた人々で、アイヌの北側の隣人といえます。日本がサハリン島の南半を統治した1905~1945年には、一部のウイルタも日本の支配を受けました。戦後に北海道へ移住したウイルタも少数いました。
ウイルタは人口300~400と、世界的にみても数が少ない民族でもあります。現在ロシア・サハリン州に住むウイルタの日常会話はもっぱらロシア語ですが、幼少期に習得したウイルタ語も覚えていて話せるという人が70歳以上でごく数名います。話者数の急激な減少とともにウイルタ語の消滅が危ぶまれ、ソ連崩壊後の1990年代から官学民の連携による保存活動が始まり、2000年代からは企業も参画して産官学民となり、教材の発行や学習機会の整備が推進されています。
このたび発行した『ウイルタ語音声資料』には、2008年から2014年にかけて、山田祥子(2022年10月~、室蘭工業大学ひと文化系領域・准教授)がロシア・サハリン州でウイルタ女性3名から採録したウイルタ語北方言による談話の音声(mp3データ)とその訳注付きテキスト21篇を収録しました。山田はこれまでも採録したウイルタ語の談話を文字に起こしたテキストを発表してきましたが、音声データを研究資料として公開するのは今回が初めてです。
本資料に収めた談話資料は、思い出話、噂話、伝統的な料理やものづくりの説明、口承文芸の再話などです。例えば、子どもの頃にホロムイイチゴ(ベリー類の一種:写真)の実を集めに行った思い出、怠けて死んだ人がいたらしい!?という噂話、伝統的な料理の作り方などは、かつてのウイルタの日常を切り取った文化的な資料としても、聞き(読み)応えがあります。 国際社会の情勢も、話者や採録者を取り巻く状況も、たえず変化し続けています。たとえ今すぐサハリンに行ったとしても2008~2014年と全く同じデータを録ることはできません。その意味で本資料は、当時の国際社会から、そして、話者のお一人ひとりからお預かりしたジャッカ(ウイルタ語で「たからもの」の意)です。
今後の展望
CD付の冊子体で発行した『ウイルタ語音声資料』は、近日中にオープンアクセスになる予定です。電子データでなく冊子体・CDでの利用を希望される方は、下記連絡先までご照会ください。
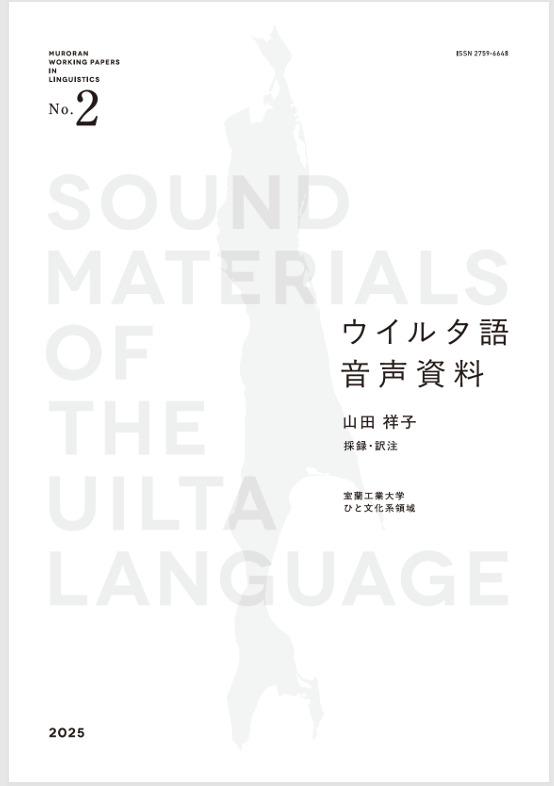


研究に関する問い合わせ
室蘭工業大学ひと文化系領域 准教授
山田 祥子
yamada@muroran-it.ac.jp
報道に関する問い合わせ
国立大学法人室蘭工業大学総務広報課秘書広報係
Tel:0143-46-5008
E-mail:koho@muroran-it.ac.jp








